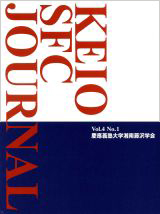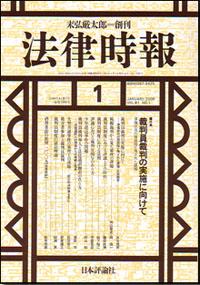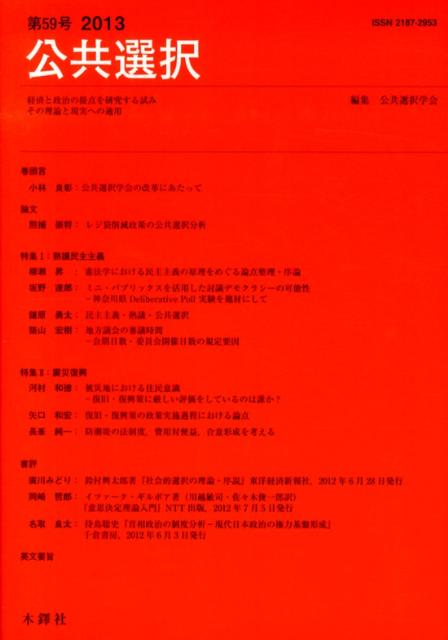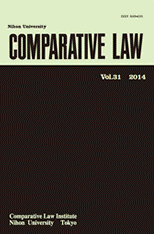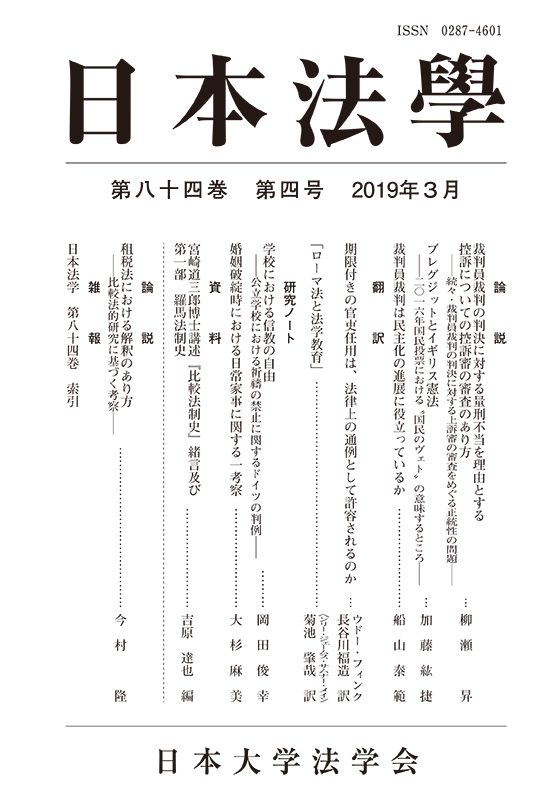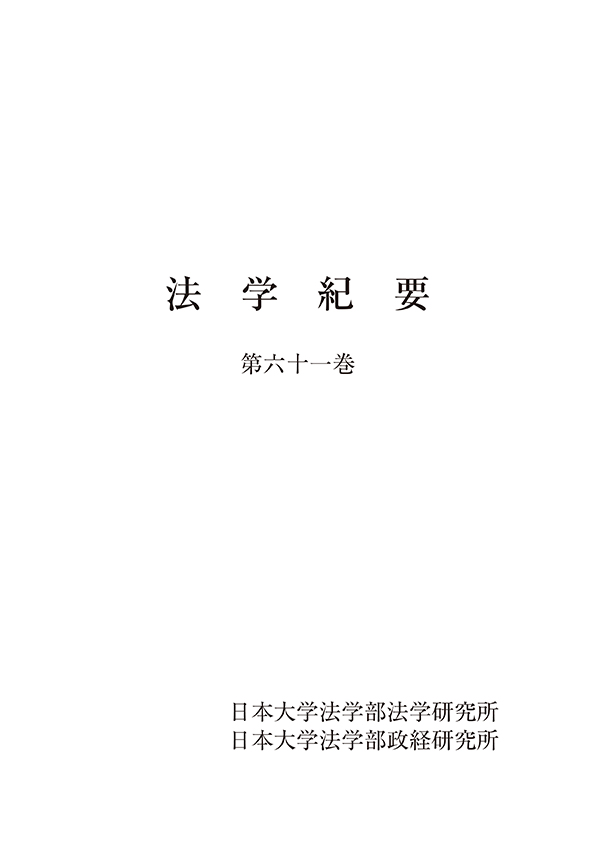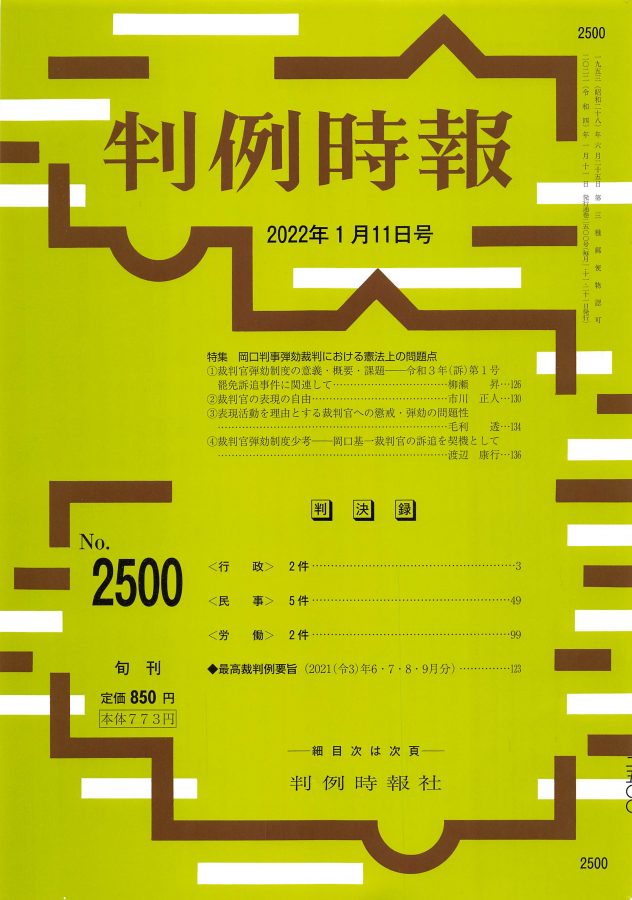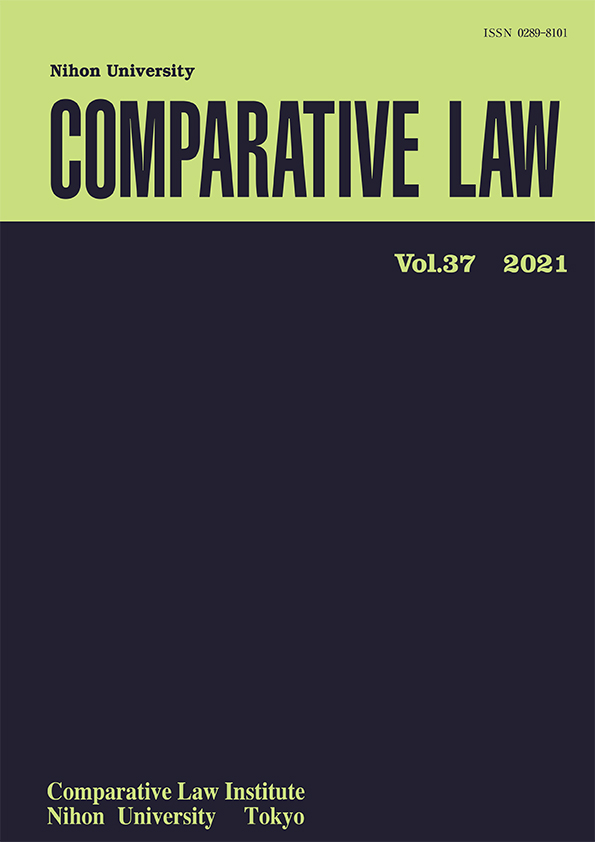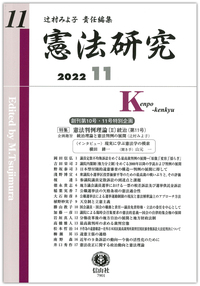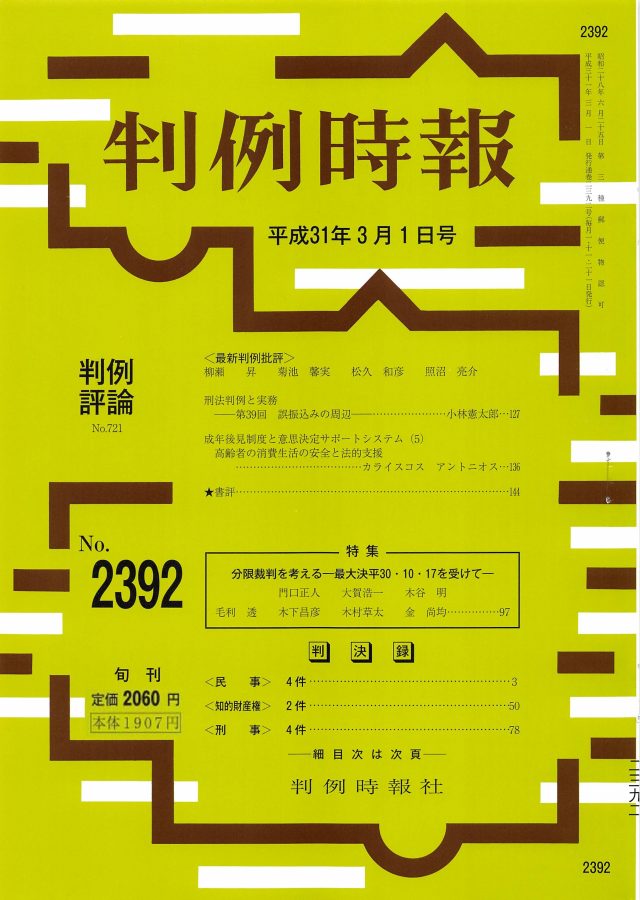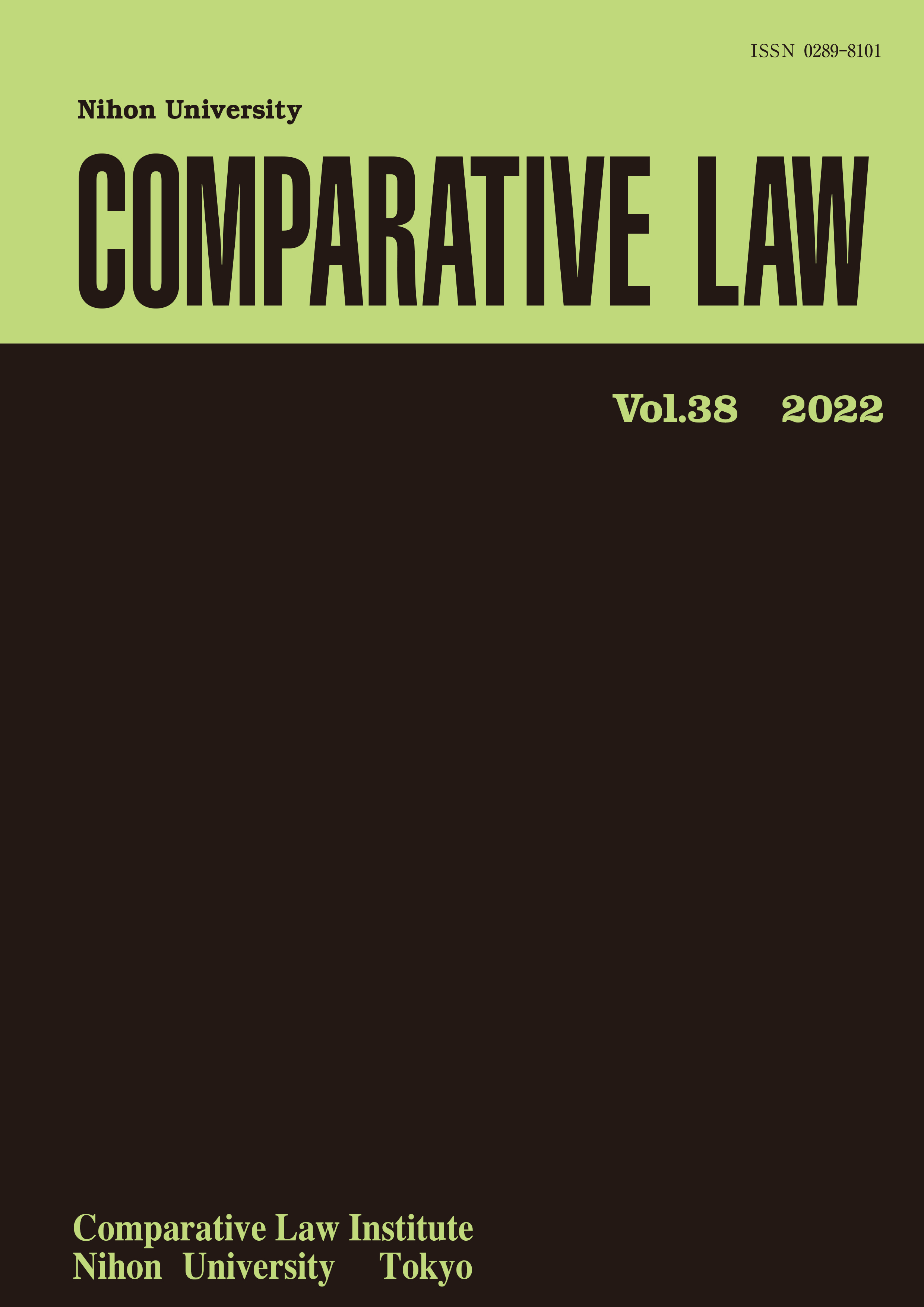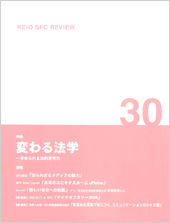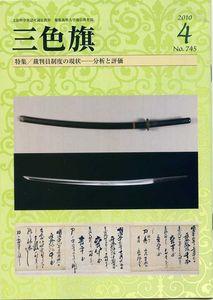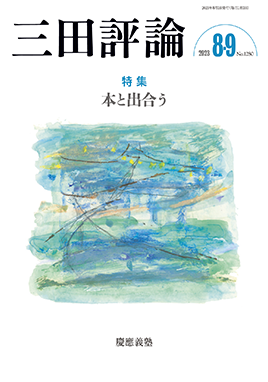Conrad G. M. Letta著、共訳(現代政治学研究会・岩崎正洋監修)、一藝社、2003年12月
担当箇所:第3部セクションVI及びVII(450-523頁)

単著(川﨑政司編)、公職研、2004年10月、全156頁
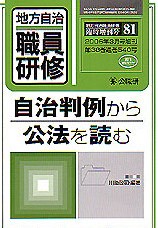
共著(川﨑政司編)、公職研、2006年3月、全264頁
担当箇所:徳島市公安条例事件(58-65頁)、泉佐野市民会館事件(74-81頁)、薬局距離制限事件(82-89頁)、塩見訴訟(106-113頁)、浦安漁港ヨット係留用鉄杭強制撤去事件(154-161頁)、宝塚市パチンコ店等規制条例事件(170-177頁)、国立マンション訴訟(除却命令等請求事件)(234-243頁)

単著(川﨑政司編)、公職研、2006年10月、全161頁

共著(川﨑政司・小山剛編)、法学書院、2007年4月、全334頁
担当箇所:集会・結社の自由(74-81頁)、職業選択の自由と規制目的二分論(82-89頁)、生存権の法的性格(106-113頁)、教育を受ける権利と教育権の所在(114-121頁)、法律と条例(178-185頁)

単著(川﨑政司編)、公職研、2007年12月、全161頁

共著(曽根泰教・大山耕輔編)、慶應義塾大学出版会、2008年1月、全315頁
担当箇所:4章「公共的討議の意義の複線化――理論群としての討議民主主義理論の生存戦略」(61-79頁)

共著(佐々木幸寿と)、学文社、2008年4月、全229頁
担当箇所:第2編「教育関連憲法判例からみる憲法解釈」(106-216頁)

共著(慶應義塾大学法学部編)、慶應義塾大学出版会、2008年12月、全401頁
担当箇所:「討議民主主義理論をめぐる議論状況」(35-62頁)
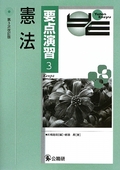
単著(川﨑政司編)、公職研、2009年4月、全171頁

共著(川﨑政司・小山剛編)、法学書院、2009年5月、全334頁
担当箇所:集会・結社の自由(74-81頁)、職業選択の自由と規制目的二分論(82-89頁)、生存権の法的性格(106-113頁)、教育を受ける権利と教育権の所在(114-121頁)、法律と条例(178-185頁)

共著(佐々木幸寿と)、学文社、2009年10月、全241頁
担当箇所:第2編「教育関連憲法判例からみる憲法解釈」(106-227頁)

共著(憲法理論研究会編)、敬文堂、2009年10月、全216頁
担当箇所:「裁判員裁判の合議体の公共的討議の場としての特質」(85-97頁)

単著、日本評論社、2009年10月、全302頁

15.Government and Participation in Japanese and Korean Civil Society
共著(Yoshiaki Kobayashi・Seung Jong Lee eds.)、木鐸社、2010年5月、全267頁
担当箇所:“The Meaning of the Peremptory Challenge in the Saiban-in (Lay Judges) Selection System in Japan: Legal Interpretation and Game Theoretical Analysis”(221-241頁) ![]()

共著(田村哲樹編)、風行社、2010年10月、全265頁
担当箇所:「裁判所における素人専門家との熟議・対話」(206-234頁)
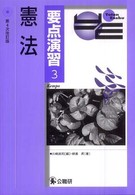
単著(川﨑政司編)、公職研、2010年10月、全173頁

共著(川﨑政司・小山剛編)、法学書院、2011年4月、全350頁
担当箇所:集会・結社の自由(74-81頁)、職業選択の自由と規制目的二分論(82-89頁)、生存権の法的性格(98-105頁)、教育を受ける権利と教育権の所在(106-113頁)、法律と条例(226-233頁)

共著(憲法理論研究会編)、敬文堂、2011年10月、全266頁
担当箇所:「司法という名の公共性の空間」(175-180頁)

共著(小谷順子・新井誠・山本龍彦・葛西まゆ子・大林啓吾編)、尚学社、2013年1月、全365頁
担当箇所:「アメリカ合衆国における弾劾されるべき罪の意義について」(278-302頁)
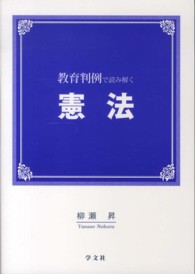
単著、学文社、2013年4月、全196頁

共著(大山耕輔監修)、ミネルヴァ書房、2013年4月、全328頁
担当箇所:「討議民主主義理論と公共政策」(187-208頁)

共著(松村格編)、八千代出版、2013年4月、全266頁
担当箇所:「憲法総論」(123-130頁)、「日本国憲法の基本原理」(131-148頁)、「憲法保障」(149-153頁)

共著(戸松秀典・今井功編)、第一法規、2013年6月、全580頁
担当箇所:「第16条〔請願権〕」(281-289頁)、「第18条〔奴隷的拘束及び苦役からの自由〕」(304-317頁)
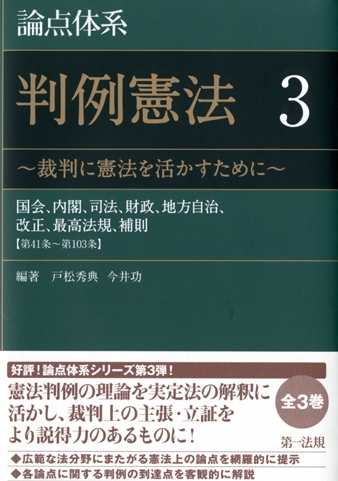
共著(戸松秀典・今井功編)、第一法規、2013年6月、全452頁
担当箇所:「第64条〔弾劾裁判所〕」(79-86頁)
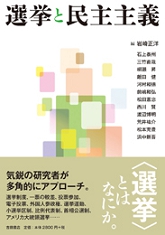
共著(岩崎正洋編)、吉田書店、2013年10月、全296頁
担当箇所:「一票の較差」(57-77頁)

共著(曽根泰教・上木原弘修・島田圭介と)、木楽舎、2013年10月、全253頁
担当箇所:「討論型世論調査の意義と概要」(67-113頁)

共著(柳下正治編)、ぎょうせい、2014年3月、全362頁
担当箇所:「「革新的エネルギー・環境戦略」策定に向けた国民的議論」(27-54頁、柳下正治と共著)

共著(川﨑政司・小山剛編)、法学書院、2014年5月、全368頁
担当箇所:集会・結社の自由(82-89頁)、職業選択の自由と規制目的二分論(90-97頁)、生存権の法的性格(106-113頁)、教育を受ける権利と教育権の所在(114-121頁)、法律と条例(242-249頁)
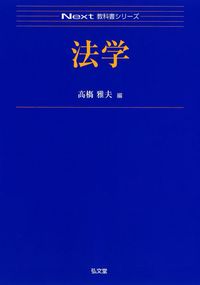
共著(髙橋雅夫編)、弘文堂、2015年2月、全304頁
担当箇所:「日本国憲法(統治)」(89-108頁)
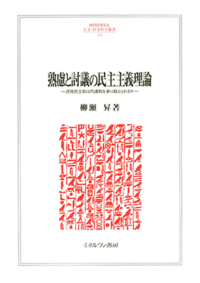
単著、ミネルヴァ書房、2015年2月、全316頁

共著(辻村みよ子・山元一・佐々木弘通編)、尚学社、2015年9月、全461頁
担当箇所:「法律上の争訟」(394-409頁)
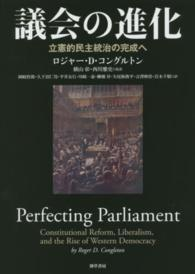
Roger D. Congleton著、共訳(横山彰・西川雅史監訳)、勁草書房、2015年10月、全450頁
担当箇所:「きめ細かな立憲的取り決め」(301-333頁)
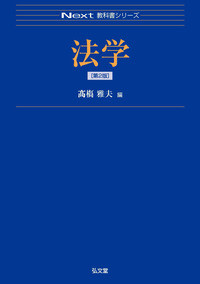
共著(髙橋雅夫編)、弘文堂、2017年1月、全304頁
担当箇所:「日本国憲法(統治)」(87-106頁)

共著(上石圭一・大塚浩・武蔵勝宏・平山真理編)、信山社、2017年6月、全832頁
担当箇所:「討議民主主義理論に基づく検察審査会制度の意義の再構成 試論」(75-95頁)
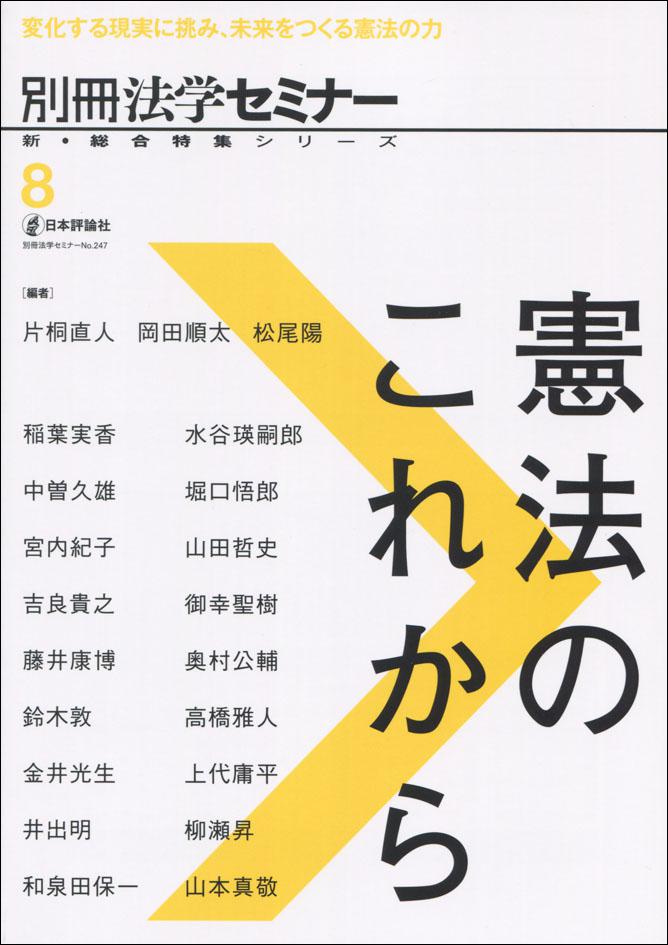
共著(片桐直人・岡田順太・松尾陽編)、日本評論社、2017年7月、全244頁
担当箇所:「国民の司法参加の制度における協働と討議の重要性」(193-200頁)

共著(岩井奉信・岩崎正洋編)、勁草書房、2017年11月、全290頁
担当箇所:「憲法改正をめぐる政治過程」(125-156頁)

共著(日本政治学会編)、木鐸社、2018年7月、全415頁
担当箇所:「国民の司法参加の正統化原理」(24-46頁)
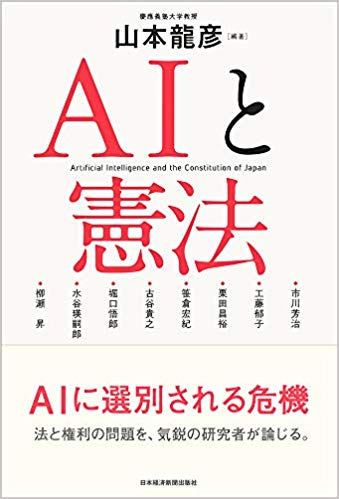
共著(山本龍彦編)、日本経済新聞出版社、2018年8月、全473頁
担当箇所:「AIと裁判」(353-392頁)
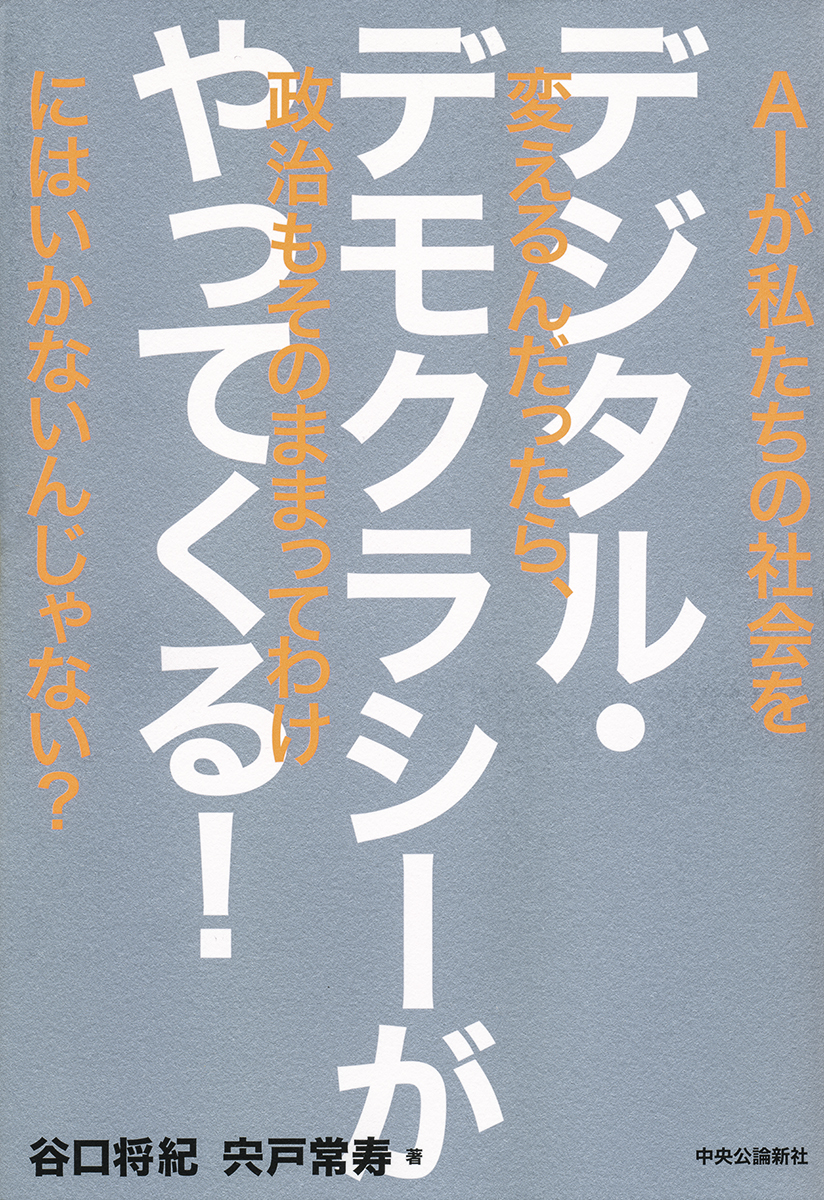
共著(谷口将紀=宍戸常寿著)、中央公論新社、2020年3月、全251頁
担当箇所:「新しい公共空間という可能性――討論型世論調査の巻」(127-157頁)

Bruce Ackerman著、共著(川岸令和・木下智史・阪口正二郎・谷澤正嗣監訳)、北大路書房、2020年5月、全436頁
担当箇所:「パブリアス」(179-236頁)
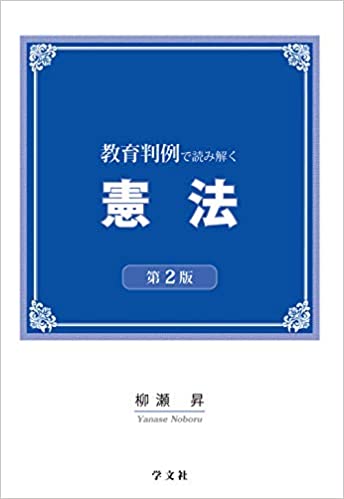
単著、学文社、2021年2月、全235頁

共著(川﨑政司・小山剛編)、法学書院、2014年5月、全368頁
担当箇所:集会・結社の自由(98-105頁)、職業選択の自由と規制目的二分論(106-113頁)、生存権の法的性格(122-129頁)、教育を受ける権利と教育権の所在(130-137頁)、国民の司法参加(186-193頁)、法律と条例(394-401頁)
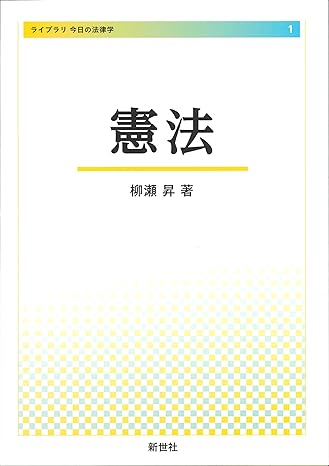
単著、新世社、2023年8月、全416頁